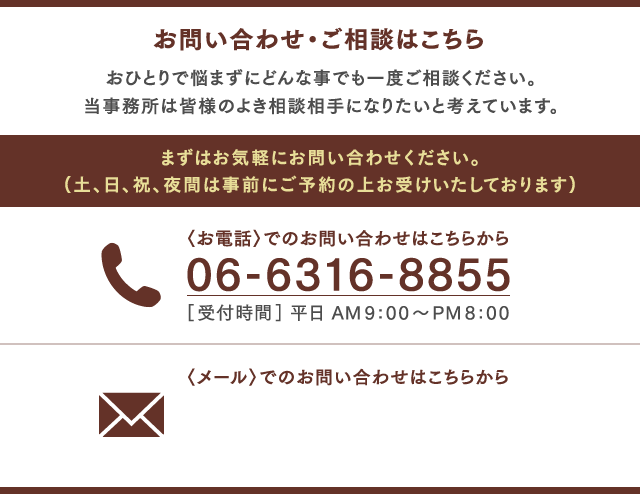退職代行Q&A(その2)
Q2.退職代行を利用する際にどういった点に注意する必要がありますか。
退職代行を利用する際には、いくつか重要な注意点があります。
下手をするとトラブルや損失につながる可能性もあるので、
以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
1. 業者の「運営主体」を確認する
退職代行には大きく分けて以下の3タイプがあります:
代行業者 特 徴 注意点
の主体
一般企業 安価でスピーディ。 勤務先との交渉は
(民間業者) 相談しやすい。 できない
(非弁行為になる可能性)
弁護士 法律的に安心。 費用は高め
トラブル対応も可能。 (5〜10万円程度)
労働組合系 労働者の代理交渉が 実績や対応範囲に差がある
合法的に可能。
2. 料金体系と追加費用をチェックする
「基本料金」だけでなく、「追加料金(有給消化交渉・書類手続きなど)」
があるかを確認。民間業者ができることが限られますので、特に注意が必要
と思われます。
契約書や注意事項をしっかり読むことが重要です。分からないときは質問
してください。
3. 退職が確実にできるか(成功率)を確認
実績・口コミ・レビューをチェック。
「絶対退職できる」と断言している業者は注意(過度な宣伝は信頼性低め)。
4. 有給休暇や未払い給与の扱い
有給消化を希望する場合、それを交渉できる業者(労働組合・弁護士)
を選ぶ。
退職金や残業代の請求をしたい場合は、弁護士一択。
5. 就業規則と契約内容の確認
就業規則に「退職は〇日前までに申し出ること」とある場合、それを無視して
即日退職するのはトラブルのもとになることも。
ただし、原則として退職の自由は認められており、最長でも2週間で退職可能
(民法627条)です。
6. 会社からの連絡対応の取り決め
「自分に連絡が来ないようにしてほしい」と要望を出せるか確認。
書類の受け取りなども代行してくれるか聞いておくと安心。
7. 退職後のサポートがあるか
離職票・源泉徴収票などの書類対応、転職支援の有無なども比較ポイント。
上記注意事項のうち、4から7の事項に全て対応できるのは弁護士だけです。
単に、退職の通知を出すだけで済む場合は民間業者で足りるといえますが、
なんらかの手続の必要性や退職に伴うトラブル処理の可能性がある場合には
弁護士が運営する退職代行に依頼するのが無難といえましょう。
この点については、Q3で詳述したいと思います。

![まずはお気軽にお問い合わせください。06-6316-8855 [受付時間 平日AM9:00〜PM8:00]](/wp/wp-content/themes/ozaki-lawoffice/commons/images/temp/tel_temp-01.gif)